原理の話などはさておき、単純に面白い写真が撮れる。そして、昔ながらの写真になる。記憶を記録にするための写真ではなく趣味で撮影する写真。いわゆる「エモい」なんて言葉が似あう。
写真というとレンズを使って集めた光を保存するようなイメージを持つ人が多いのではないかと思います。なぜレンズを使うか?それはレンズを使うと多くの光を集められるので撮影しやすいし、性能がいいレンズを使えば解像度も高くできるし、画角も設定できます。しかし、このピンホールはレンズを使いません。一点を通過する光のみを使うため暗い(=シャッター時間を長くしなければならない)し、像もはっきりしません。それでもやってしまう魅力があります。
ピンホール撮影をした作品
ピンホールは何とも言語化しがたい魅力のあるもので、意図もなく写真を撮ることが多い自分は「作例」という言葉を違和感なく使っています。しかしここでは作品としたいです。

はじめてピンホール撮影をした時の写真

これは多重露光ではありません。複数の穴をあけることでずらして重ねることができます。展開したマトリョシカをずらして写した作品です。

シャッターを開いたままライターを振り回しました。
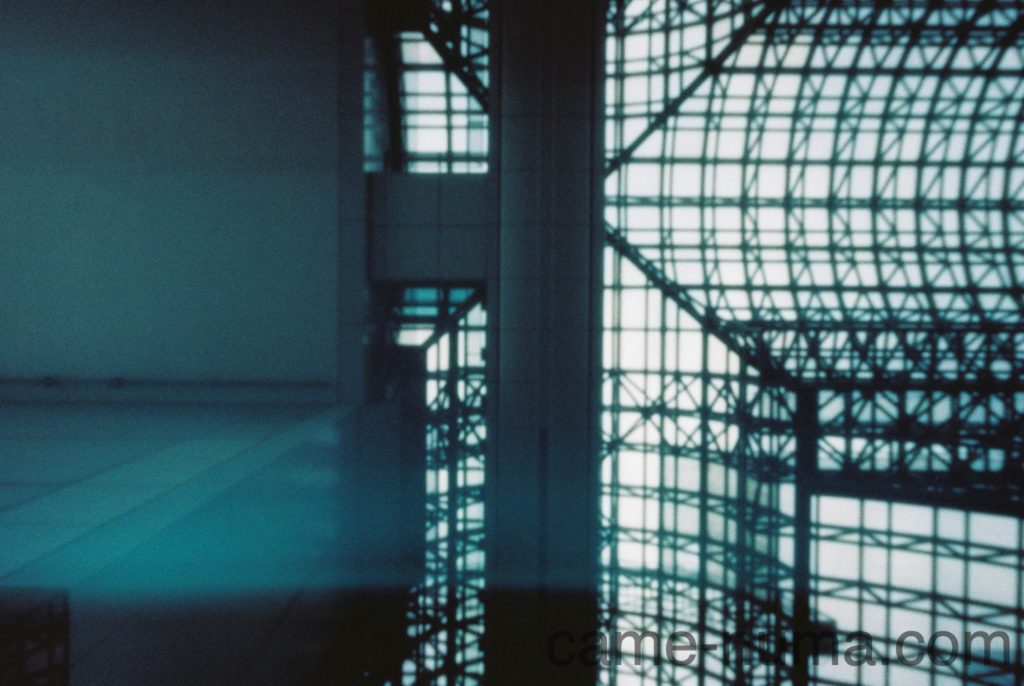
大学時代を過ごした京都
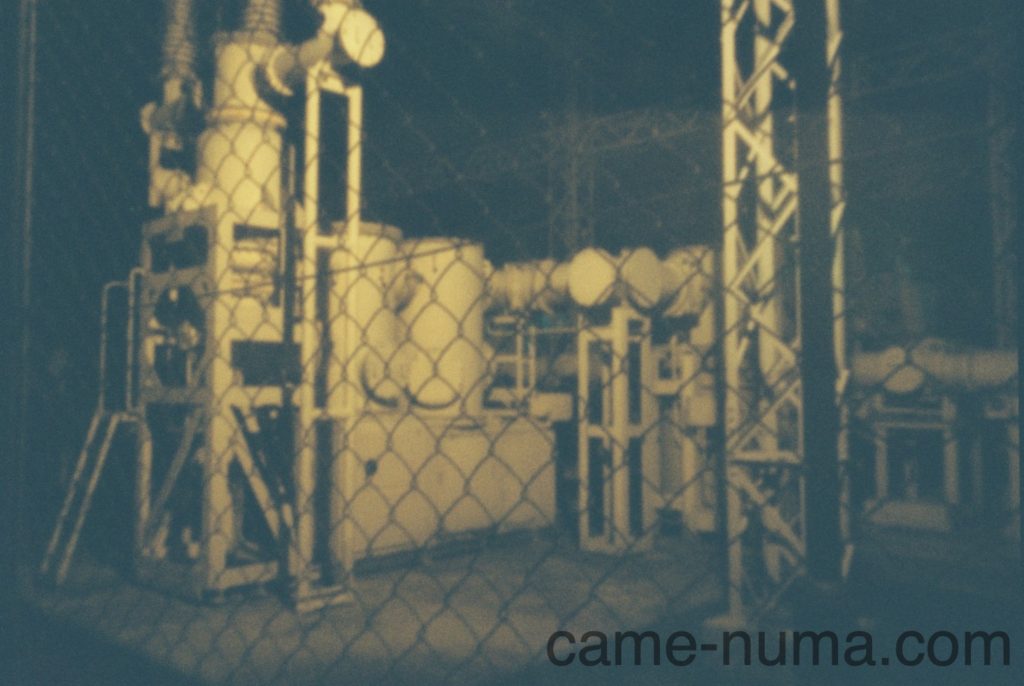
この写真、ISO800の高感度フィルムを使って約30分露光しています。
ピンホールカメラ作り方
ピンホールは簡単に作れます.適当な金属の薄い板に針で小さな穴をあけます。穴をあけた金属板はレンズ代わりです。ドリルで穴をあけたレンズキャップにつければ撮影できます。



内側からマスキングテープで貼って申し訳程度に黒く塗っています。
画角は撮像面からピンホールの距離、レンズキャップにピンホールをつけるならば、フランジバック長で画角が決まるというイメージです。レンジファインダーやミラーレスだと広角、一眼レフだと望遠といった感じです。コピーライカに使用して30~35mm程度の画角という印象。
ピンホールの作例

ナンバープレートを隠さないといけないほどにははっきり読める程度に写ります。

様々な要素で色や写りが変化する。そしてそれを予測するのは難しい。そんな面白さがあります。

この写真は3秒程度の露光です。

そしてこちらは10秒程度
ピンホールほど長い露光をする場合、単純に同じISO感度のデジタルの自動露出と同じ時間のシャッターというわけにはいきません。詳しくは興味があれば調べていただきたいですが、「相反則不軌」というもので、長いシャッター時間の場合、時間を倍にすれば1段上がるという基本が成り立たないのです。時間を倍にしても1段も上がらず、従来の感覚で撮影してしまうとアンダーになってしまうんです。なので、ネガの場合長めに露光しておかないと痛い目にあいます。ちなみに自分はISO400であれば、大体日中で10秒というざっくりした感覚で撮っています。
沼津へ行った時の写真
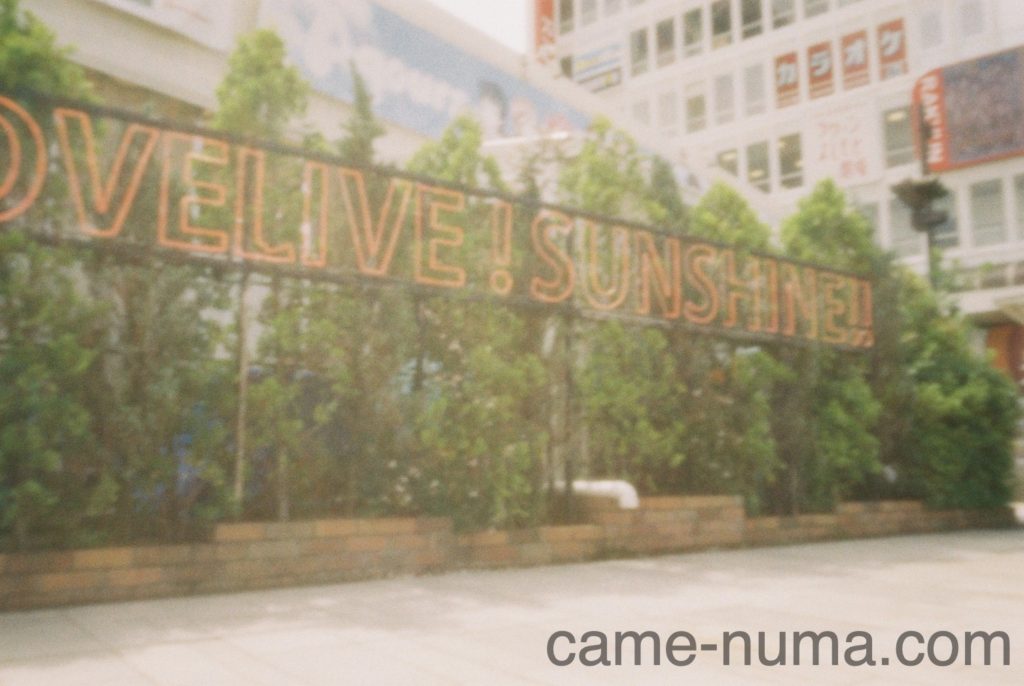






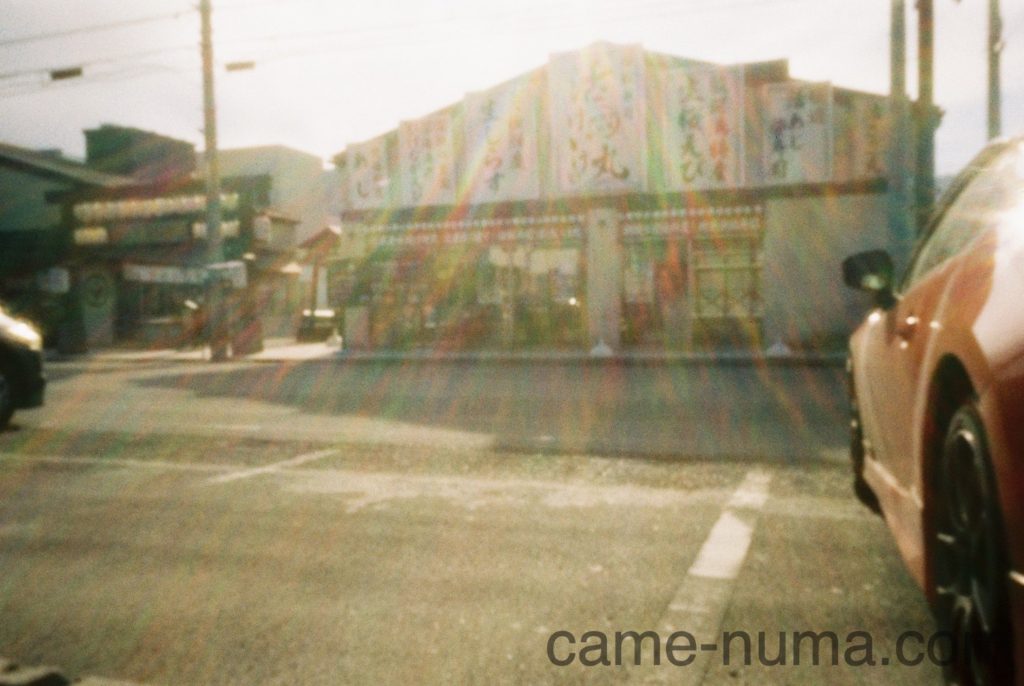


名古屋の写真


この写真は窓の内側から撮っています。ピンホールにはレンズと異なり「ピント」という概念がありません。そのためいかなる距離も原理的には同じように写ってしまいます。そのため窓の汚れがそのまま写っています。
京都の写真
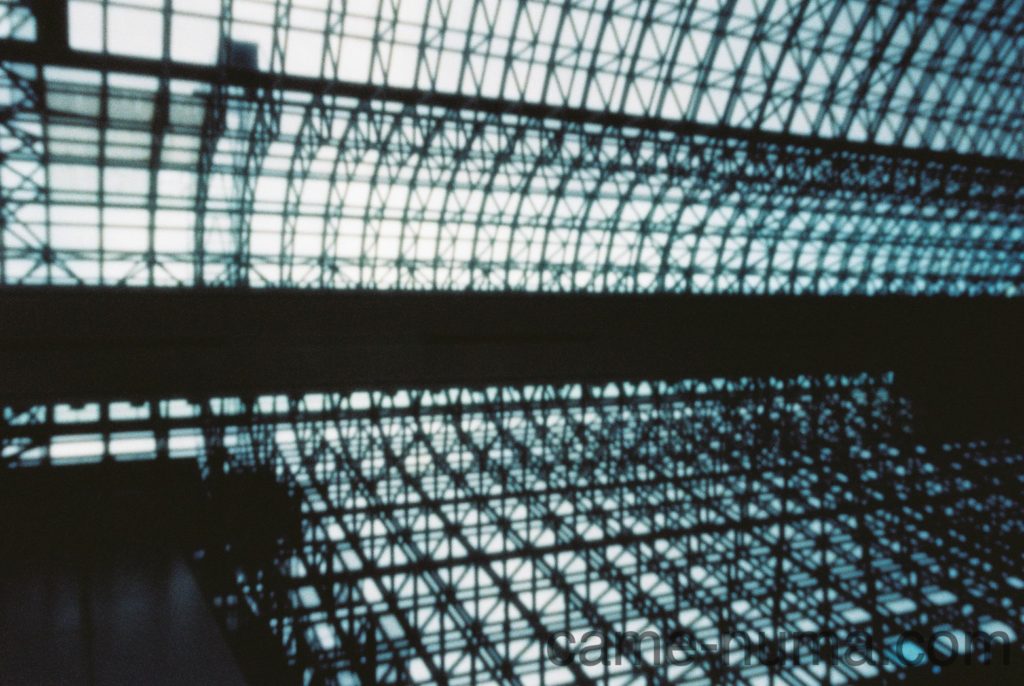
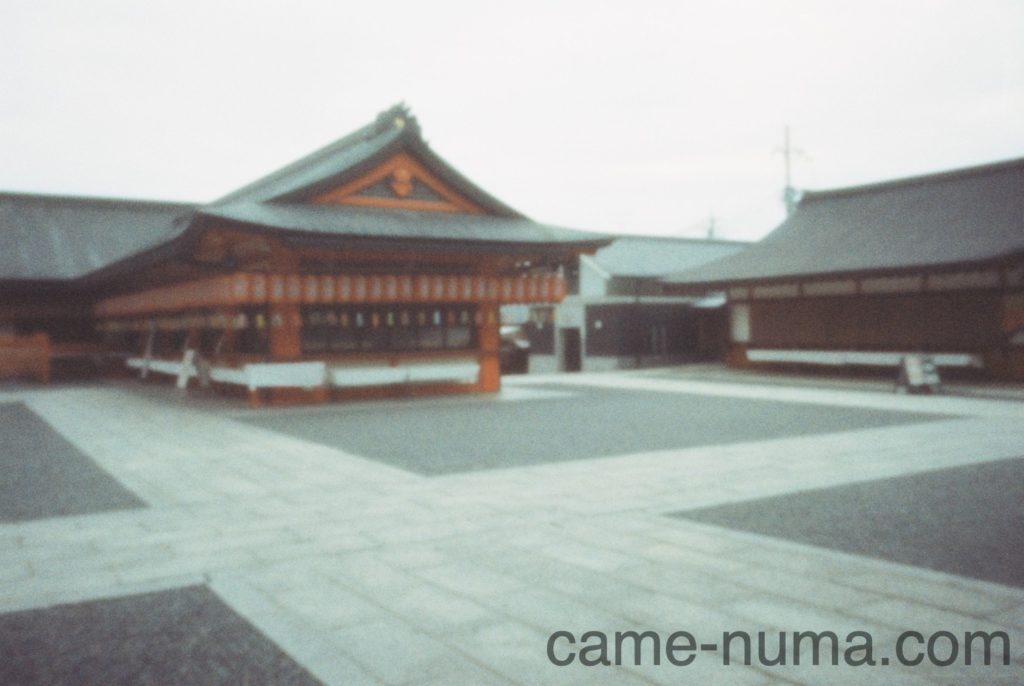


結論
写真の原点ともいえるピンホール。素朴で味のある写真。ピンホールは楽しい。ぜひやってみてください。




コメント